はじめに
「先生、ついでに銀行でお金下ろしてきてくれへん?」
「入院するから、病院まで付き添ってほしいんやけど…」
「夜中に警察から電話が…。今から迎えに来れますか?」
ケアマネージャーとして日々奮闘する中で、このような「本来の業務ではないお願い」にどう対応すべきか、頭を悩ませた経験はありませんか?
この記事では、長年主任ケアマネとして現場に立ってきた私が、どこまでがケアマネの業務で、どこからが他事業所や専門職に繋ぐべき業務なのか、その境界線と具体的な対処法について、実践的に解説していきます。
この記事を読めば、あなたを悩ませる「シャドウワーク」から解放され、自信を持って利用者と向き合えるヒントがきっと見つかります。
改めて確認!ケアマネージャーの本来の業務とは?
まず、私たちの専門性の原点に立ち返りましょう。ケアマネージャーの根幹業務は「利用者の意思に基づいたケアプランを作成し、介護保険サービスが適切に提供されるようマネジメントすること」です。
具体的には、
- 利用者や家族からの相談対応とアセスメント(課題分析)
- ケアプランの作成・交付・説明・同意
- サービス担当者会議の開催
- 各サービス事業者との連絡・調整
- モニタリング(サービスの実施状況の確認と評価)
- 給付管理業務
などが中心です。私たちはあくまで、利用者が自立した生活を送れるよう、様々な社会資源を繋ぎ合わせる「橋渡し役」であり、直接的な身体介助や、生活の万事屋ではありません。
なぜ断れない?ケアマネを悩ませる「シャドウワーク」の具体例
では、なぜ多くのケアマネが本来の業務範囲を越えた「シャドウワーク」を抱え込んでしまうのでしょうか。
シャドウワークの典型的な例
皆さんも、一度は経験があるのではないでしょうか。
- 金銭管理: 銀行での入出金代行、公共料金の支払い
- 買い物代行: 日用品や食料品の購入
- 各種手続き代行: 介護保険外の書類提出(郵便局、銀行、役所など)、障害者手帳の再発行手続き
- 送迎・付き添い: 通院時の送迎、院内での付き添い
- 緊急時対応: 深夜の徘徊発見時の警察からの呼び出し、救急搬送時の同行
- その他: 役所の予約電話、近隣トラブルの相談対応など
シャドウワークを引き受けてしまう背景
これらの依頼を断り切れない背景には、ケアマネならではの切実な事情があります。
- 「冷たい人だと思われたくない」という想い: 断った結果、利用者や家族との関係性が悪化したり、担当変更を申し渡されたりすることへの恐れ。
- 事業所の経営的なプレッシャー: 利用者数が給与や評価に直結するため、一人でも失いたくないという現実。
- 「自分がやれば早い」という責任感: 他の制度やサービスを探して調整するより、自分で動いた方が早いと考えてしまう。
こうした想いから、つい「今回だけですよ」と引き受けてしまい、それが常態化してしまう…。この負のループこそが、私たちを疲弊させるシャドウワークの正体です。
「断る」ではない!「繋ぐ」ための実践的アプローチ
では、どうすればいいのでしょうか。答えは、「専門家として毅然と断る」のではなく、「より適切なサービスや制度に専門家として繋ぐ」ことです。
① 「恩を売ってから繋ぐ」テクニック
全く対応しない、というのは信頼関係を損なうリスクがあります。そこでおすすめなのが**「初回だけあえて対応し、恩を売る」**というアプローチです。
実践例:
「(通院同行を終えて)〇〇さん、無事に終わって良かったですね。ただ、こうした通院の付き添いは、本来はケアマネジャーの業務ではないんです。もし今後も必要であれば、ヘルパーさんに自費でお願いできるサービスがありますから、一度相談してみませんか?その方が、〇〇さんも気兼ねなく頼めると思いますよ。」
ポイントは、「今回だけの特別対応であること」「本来の業務ではないこと」「次回以降の代替案があること」をセットで伝えることです。これにより、利用者の「困った」を解決しつつ、次からは適切なレールに乗せることができます。
② 具体的な「繋ぎ先」を知っておく
ケアマネは一人で全てを抱える必要はありません。それぞれの「プロ」にバトンタッチしましょう。
- 金銭管理や重要な契約・手続き:
- 成年後見制度: 判断能力が不十分な方のための法的な支援制度。
- 日常生活自立支援事業(社会福祉協議会): 福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理をサポート。
- 買い物・掃除・通院同行など:
- ヘルパー(訪問介護)の保険外(自費)サービス: 介護保険の範囲外の要望に柔軟に対応してくれます。
- 緊急時の対応:
- 24時間対応の訪問介護や定期巡回・随時対応型訪問介護看護: 夜間や緊急時の連絡・対応体制を整備できます。
③ 自分を守る最強の武器は「記録」
利用者とのやり取りは、どんな些細なことでも必ず記録に残してください。これが、あなたの身を守る最大の武器になります。
- いつ、誰から、どんな依頼があったのか?
- それに対して、どのように説明し、どこに繋いだのか?
口頭でのやり取りは「言った」「言わない」のトラブルになりがちです。音声入力などを活用し、リアルタイムでメモを残す癖をつけましょう。誤字脱字があっても構いません。後で清書すれば良いのです。まずは「記録した」という事実が重要です。
業務効率化が、心と時間の余裕を生む
ここまで解説したような丁寧な「繋ぎ」の対応をするには、心と時間の余裕が不可欠です。そのためには、本来の業務における事務作業を徹底的に効率化することが欠かせません。
- Googleカレンダーでのスケジュール管理
- 音声入力を活用した記録作成
- チャットツールでの多職種連携
こうしたITツールを積極的に活用し、1分でも多く「考える時間」「調整する時間」を生み出しましょう。事務作業の時間が減ることは、精神的な安定に直結します。
まとめ:あなたは「調整役」一人で抱え込まないで。
ケアマネージャーの業務範囲は、時に曖昧で、その責任の重さに押しつぶされそうになることもあります。
しかし、忘れないでください。あなたの役割は「たった一人で全てを解決するスーパーマン」ではなく、利用者を支えるチームを指揮する「優秀な司令塔(コーディネーター)」です。
業務の線引きに悩み、シャドウワークに追われる状況は、結果的に本来行うべきケアマネジメントの質を低下させ、どの利用者にとっても不利益になりかねません。
一人ケアマネで悩んだら、地域包括支援センターに相談するのも一つの手です。(もちろん、包括によって考え方が違う場合もありますが…)
この記事が、あなたが「抱え込むケアマネ」から「上手に繋ぐケアマネ」へと進化し、専門職として長く輝き続けるための一助となれば、これほど嬉しいことはありません。
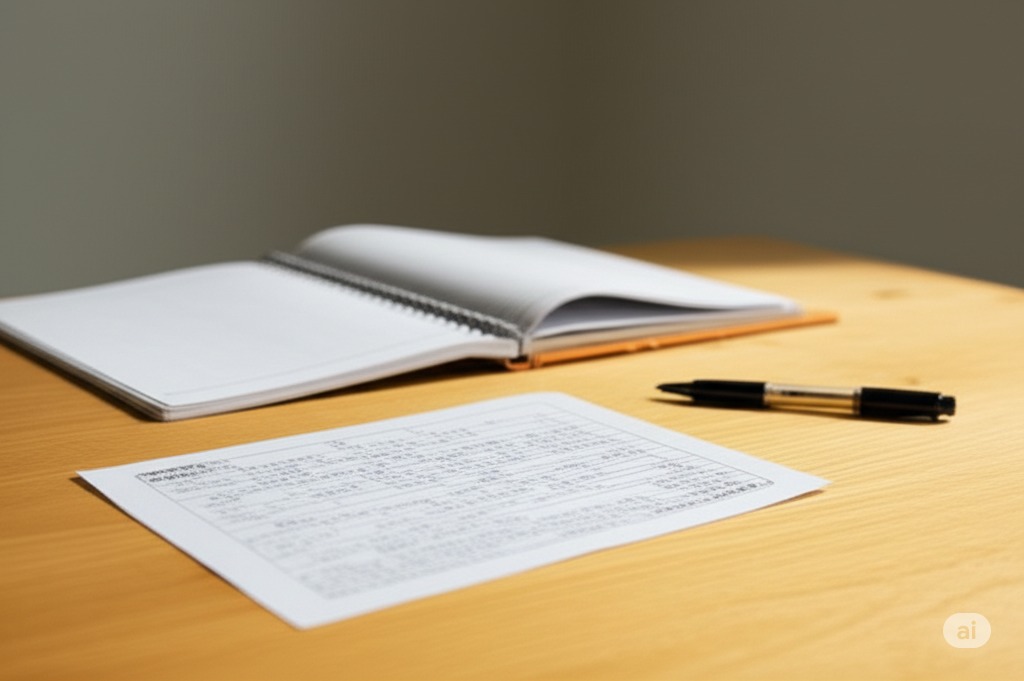
コメント